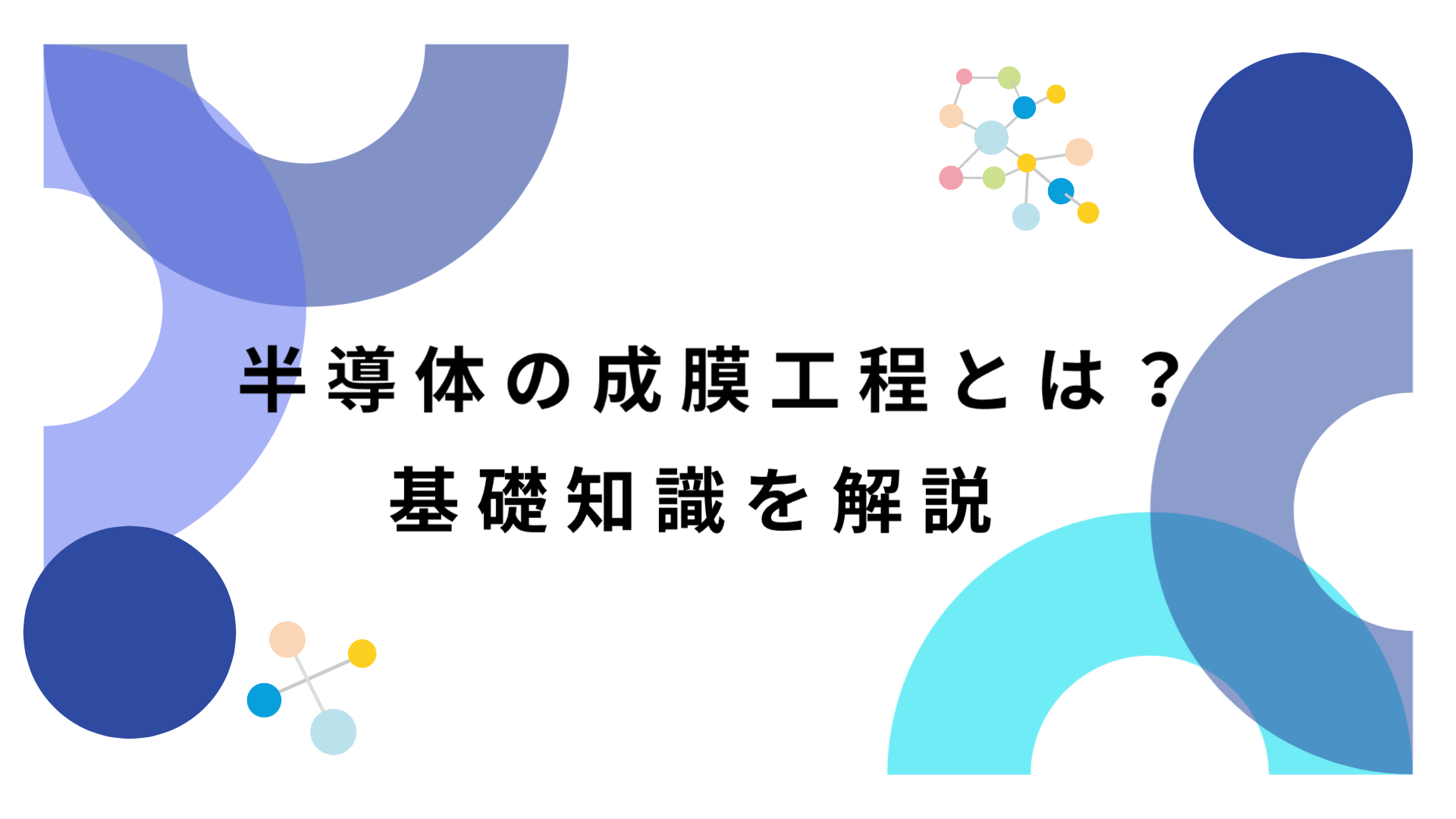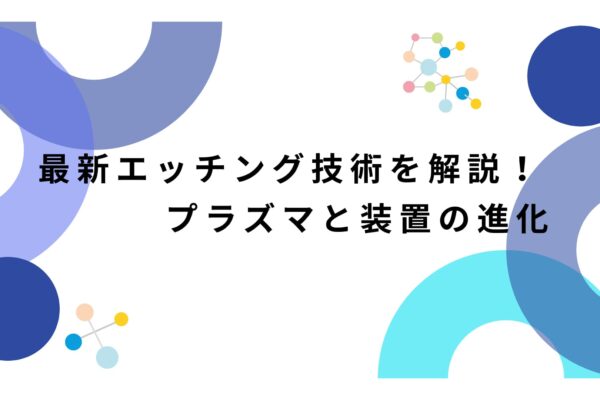私たちの生活に欠かせないスマートフォンやパソコン、家電製品の多くに搭載されている半導体チップ。その内部では、驚くほど複雑な微細構造が機能しています。この微細な構造を形作るうえで不可欠なのが、薄膜を何層にも積み重ねる「成膜(せいまく)」技術です。
成膜は、半導体製造の「前工程」における主要な技術の一つであり、リソグラフィ(回路パターン形成)と並び、チップの性能と信頼性を決定づける重要な役割を担っています。ガラスやシリコン基板の表面に、紙の厚さの数百〜数万分の1に相当するわずか数ナノメートルから10マイクロメートル程度の膜を形成することで、絶縁、導電、保護といった多様な機能が付与されます。
本記事では、この奥深く繊細な成膜技術の基礎から、使用される材料、実現する装置の種類、さらには製造プロセス全体までを解説していきます。
半導体の成膜とは?
半導体チップは、絶縁膜、金属膜、半導体膜など、多様な機能を持つ薄膜を何層も形成し、それらを加工することで作られます。この薄膜を形成するプロセスを成膜(せいまく)と呼び、リソグラフィと並ぶ前工程の主要な技術です。
半導体製造で広く用いられているのは、材料を気化させて化学反応により分解・堆積させるCVD(化学的気相成長)法です。しかし、その他にも用途や目的に応じて様々な成膜方法があり、使い分けられています。
近年、半導体の微細化が進むにつれて、配線材料も従来のアルミニウムから、より電気抵抗の低い銅へと変化するなど、新しい材料が導入されています。これに伴い、それらの新材料に対応できる成膜法も開発され、活用されています。
薄膜と成膜との違い
成膜とよく似た語句に、薄膜(はくまく)があります。
薄膜とは、ガラスやシリコンの基板などの表面に、ごく薄く形成される膜のことです。一方で成膜とは、その薄膜を形成するプロセスのことを指します。
薄膜はその名の通り非常に薄い膜を指し、特に厚さが10マイクロメートル以下のものを指すのが一般的です。紙は60〜70マイクロメートル、やアルミホイルは10〜60マイクロメートルほどであり、比較するとその薄さは際立ちます。
また、さらに薄いものでは数ナノメートルという極限の薄さになります。その薄さゆえに、薄膜はそれ単独で存在することはできず、必ず基板の上に形成されます。
成膜で使用される材料と役割
成膜加工に用いられる基板にはいくつかの種類があり、膜の材料と組み合わせて多岐にわたる用途に対応します。主な材料には、下記のようなものがあります。
- 樹脂… 非粘着性や耐摩耗性を付与したい場合に用いられる。軽量で加工しやすいのが特長。
- シリコン…耐熱性、絶縁性、耐圧性といった優れた特性を兼ね備えている。そのため、摩耗や熱による破損を避けたい対象物、特に半導体デバイスの基板として広く採用されている。
- 金属…アルミニウム(Al)をはじめとする汎用性の高いものから、熱伝導性の高いAg(銀)などが使用せる。金属の表面に成膜処理を行い、色を表現したり配線を処理したりすることが可能。
- ガラス…光学部品やディスプレイなど、透明性や光学特性が求められる場合に用いられる。モバイル機器や半導体チップの部品など。
- セラミックス…高温下でも安定した動作が求められるときや、耐薬品性が必要な場面で用いられる。
このように、材料によって特徴は大きく異なります。それぞれの用途に合わせて、適切な材料を選定・加工を施すことが非常に重要です。
成膜の方法
薄膜を形成する方法は多岐にわたり、その用途や目的に応じて最適な手法が選択されます。ここでは、主要な方法をご紹介しましょう。
PVD(物理的気相成長)法
PVD法とは、成膜材料を物理的に気化させ、基板上に堆積させる方法です。主に金属膜やバリア膜の形成に用いられます。薄膜した材料を物理的に蒸発させるため「物理気相成長」とも呼ばれています。
また、材料の飛散方法により、PVD法は「スパッタリング」「蒸着」「イオン化蒸着」「イオンビーム」に分類されます。それぞれの特徴は以下の通りです。
| 方法 | 特徴 |
| スパッタリング | ・放電によるプラズマ中にできたイオンを、成膜材料に高速でぶつけ、ターゲットから原子・分子を跳ね飛ばす。はね飛ばされた成膜材料が基板へ飛んでいき薄膜を形成する。 ・高融点金属や合金、絶縁体など、蒸着法では困難な材料でも成膜が可能で、非常に広範囲な成膜材料に対応できる。 |
| 蒸着法 | ・真空にした容器の中で、金属や酸化物などの成膜材料を加熱・蒸発させ、対向する基板表面に凝着させて薄膜を形成する。 ・比較的シンプルな装置で成膜が可能ですが、基板の形状によっては膜厚の均一性が得にくい場合があります。 |
| イオンプレーティング (IP) 法 | ・原理的には蒸着法とほぼ同じだが、蒸着粒子をプラズマ中を通過させることで蒸発材をイオン化させる。成膜させる基板にマイナスの電圧をかけ、イオン化させた蒸着材を加速させながら基板に衝突させることで薄膜を形成する。 ・高密着性が必要な金属膜やバリア膜(TiN、TaNなど)の形成に利用されることがある。 |
加工する素材や性質によって、適切な製造方法は異なります。
CVD(化学的気相成長)法
CVDは、成膜したい元素を含む気体(反応ガス)を基板表面に送り込み、基板表面または気相中で化学反応を起こさせることで薄膜を堆積させる方法です。主に絶縁膜、ポリシリコン膜、金属膜の一部形成に用いられます。主に以下のような手法があります。
| 方法 | 特徴 |
| 熱CVD | ・成膜したい元素を含む気体(反応ガス)を反応室に導入し、基板を高温に加熱することで、ガス分子が熱分解したり、基板表面で他のガスと化学反応を起こしたりして、目的の薄膜を形成する。 ・高温でのプロセスが多いものの、高品質な薄膜が形成できる。 |
| プラズマCVD | ・反応管内を減圧し、プラズマを発生させることで、反応ガスを分解・活性化し、成膜を促進する。プラズマのエネルギーを利用するため、熱CVDよりも低い温度で成膜できる。 ・低温プロセスなので、熱ダメージを最小限に抑えられる。 |
| 原子層堆積(ALD)法 | ・ALD法はCVD法の一種だが、そのプロセスはより精密である。各ステップの反応が自己飽和するため、導入するガスの量に依存せず、正確な膜厚制御が可能。 ・ほぼ原子1層分ずつ成膜できるため、精緻な成膜制御ができる。 |
近年の半導体製造では、CVD法をベースに、より精密で均質な膜を作る、ALD法を用いる機会が増加している傾向にあります。
成膜装置の種類
成膜装置は、シリコンウェーハなどの基板上に、狙い通りの特性を持つ非常に薄い膜を形成するための装置です。半導体デバイスの製造において、この成膜工程は中心的な役割を担っており、デバイスの性能や信頼性を大きく左右します。ここでは、主な装置の種類を紹介しましょう。
バッチ式成膜装置
バッチ式成膜装置は、真空チャンバー内に複数の基板を一度にセットし、それらを回転させながら成膜を行うのが特徴です。基盤形状の自由度が高く、さまざまな形やサイズの基板に対応できます。
スパッタリングや真空癒着に柔軟に対応できるほか、比較的小ロットでの生産が可能。試作品を作ったり、少量生産をしたりするのに適しています。
インライン式成膜装置
基板を装置内へ連続的に搬送しながら、次々と成膜していく方式です。基盤を途切れなく処理できるため、生産ラインに組み込むことを前提としています。
大量生産に有利であるほか、プロセス条件を安定させやすいのも特徴。均一な品質の膜を連続して形成できます。さらに、人手を介する作業を削減できるため、人件費削減にも大きく寄与します。
ロールtoロール式成膜装置
ロールtoロール式成膜は、ロール状に巻かれた長いフレキシブル基板を真空中で連続的に巻き出し、成膜処理を施した後、再びロール状に巻き取る革新的な成膜方法です。
この方式の最大の利点は、その圧倒的な生産効率にあります。大面積の薄膜を非常に高速で形成できるため、製造コストの削減と生産能力の大幅な向上が可能です。また、フレキシブルな基板に特化しているため、曲げられるディスプレイや太陽電池といった次世代製品の製造に欠かせません。
用途は多岐にわたり、フレキシブルディスプレイ、タッチパネル、フレキシブル太陽電池をはじめ、電池電極、高機能な包装材、各種機能性フィルムなど。柔軟性が求められるような、幅広い分野で活用されています。この技術は、未来の電子デバイスやエネルギー分野の発展を支える基盤となっています。
円筒内面式成膜装置
円筒内面式成膜装置は、その名の通り、パイプやチューブといった円筒状の基板の内側に薄膜を形成するために特化して設計された装置です。
この装置の大きな利点は、外側からはアクセスしにくい円筒内部に、均一で高性能な機能性薄膜を精密に形成できる点にあります。これにより、通常の方法では実現が難しい特殊な製品の製造が可能となります。
主な用途としては、光を効率よく集めるための反射鏡や、特定の波長のみを透過・遮断する光フィルターといった光学素子の製造が挙げられます。また、特定の化学反応を促進・抑制するための化学反応装置のライニングや、微細な計測を可能にする特定のセンサー部品など、円筒内部に高度な機能性を持たせる必要がある製品でその真価を発揮します。
この技術は非常に専門性が高く、小型から大型まで対応可能ですが、その特殊性ゆえに、装置を保有している企業は限られているのが現状です。
成膜加工の一般的なプロセス
成膜加工は、繊細な部品を扱うため、高度な技術が求められます。一般的に次のようなプロセスで進められます。
基板材料をチェックする
まずは、自社調達品や顧客から預かった基板材料の数量と品質を確認します。
非常に小さな傷や欠損があるだけでも、その部品を使用することはできません。入念にチェックすることで、生産ラインへの不良品流入を防ぎ、安定した製品供給の基盤を築きます。
基板材料の精密洗浄をする
成膜前には、洗浄液や超音波のキャビテーション効果を利用して、基板表面の汚れを徹底的に除去します。
一見すると、この工程は極めて地味に見えるかもしれません。後の薄膜の密着性や品質に直結するため、高品質な成膜には不可欠といえます。
薄膜コーティング(成膜)
品質チェックや洗浄が完了したら、いよいよ成膜加工です。洗浄された基板材料は、クライアントのニーズに合わせた適切な方法で薄膜が形成されます。
具体的には、基板のサイズ、形状、材質、さらには試作か大量生産かといった生産量などのニーズが挙げられます。そうした要望に合わせて、最適な成膜装置(バッチ式、インライン式、ロールtoロール式、円筒内面式など)が選択され、成膜が実施されます。
完成品の厳格な検査
成膜が完了した製品は、技術者の目視や触診、そして機械を用いた入念な検査が実施されます。製品によっては、わずかな傷やムラが性能に致命的な影響を及ぼすこともあるため、細部まで見逃さずに確認します。
常に高性能・高品質な製品を安定供給するため、この最終検査は極めて重要です。光学薄膜は、光学機器、半導体、医療機器など幅広い分野で使用され、その品質が最終製品の性能を大きく左右します。
まとめ
本記事では、半導体製造における核となる技術である成膜について、その基礎から応用までを詳しく解説しました。紙の厚さの数万分の一に過ぎない極薄の膜が、半導体チップの性能を支えていることに、驚かれる方もいるでしょう。
成膜に使用される材料は、半導体基板となるシリコンをはじめ、回路形成のための金属や、絶縁を担うガラスなど、多岐にわたります。これらの材料は、目的とする機能や特性に応じて厳選されます。
成膜方法としては、物理的な力で堆積させるPVD法、化学反応を利用するCVD法が主要です。それぞれの方法は独自の特性を持ち、用途に合わせて使い分けられます。また、生産量や基板の形状に応じて、バッチ式、インライン式、ロールtoロール式、円筒内面式といった多様な成膜装置が活用されています。
最終的に、高品質な薄膜製品を生み出すためには、材料の厳密なチェック、精密な洗浄、そして成膜後の厳格な検査といった一連のプロセスが不可欠です。これらの多岐にわたる技術と工程が連携することで、私たちの暮らしを豊かにする最先端の半導体デバイスが日々生み出されています。