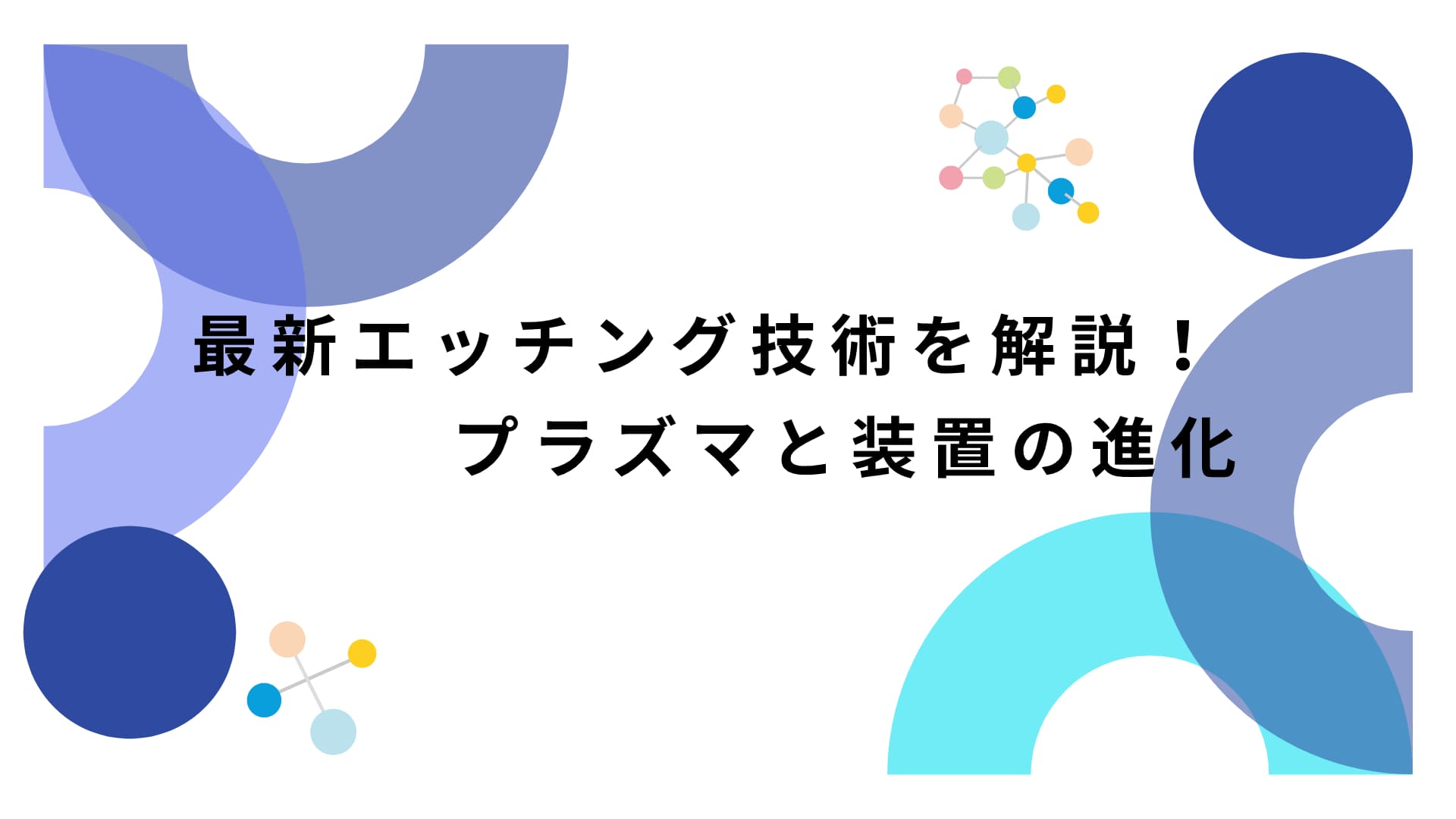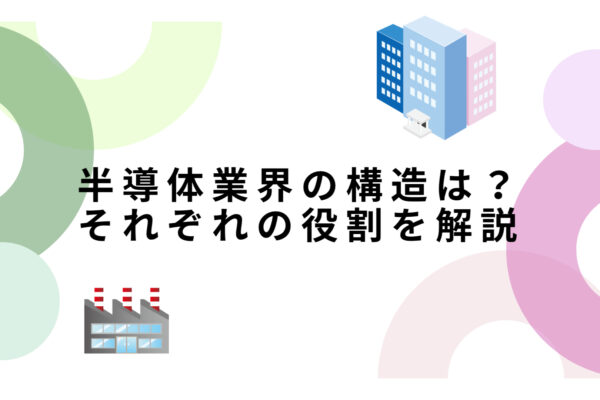半導体製造におけるエッチングは、微細化と3次元構造化の進展により、ますます高精度と低ダメージ化が求められています。特にドライエッチングでは、プラズマの制御技術が加工品質を左右し、装置構造の工夫や材料特性への適応が鍵を握ります。
本記事では、プラズマの原理から等方性・異方性エッチングの違い、主要な装置方式やメーカー動向までを体系的に解説します。
高密度・低ダメージ化が求められる理由
半導体の高集積化が進み、1ナノメートル単位での加工精度が求められる現在、エッチング工程では微細構造を正確に形成するだけでなく、ウェハへの熱的・電荷的ダメージを最小限に抑えることが重要です。
微細化が進むほど、わずかなイオン衝撃でも欠陥や電気特性の劣化につながるため、デバイス性能を維持するには低エネルギーで高密度なプラズマ生成と、それを安定的に制御する高度なプロセス技術が欠かせません。
エッチングに欠かせないプラズマ技術
プラズマはドライエッチングの心臓部です。物質を電離させた「第四の状態」として、反応性の高いイオンやラジカルを生成し、薄膜の加工を行います。
プラズマの基本原理は、物質は加熱により固体から液体、気体、そして電子とイオンが分離したプラズマ状態へと変化します。高周波電力を加えることでガス分子が電離し、電子が衝突と再結合を繰り返す中で安定したプラズマが形成されます。半導体ではこの反応性を利用し、ウェハ上で選択的な化学反応を引き起こします。
反応性イオンエッチング(RIE)の役割
半導体加工では、プラズマ中のイオンやラジカルを利用する反応性イオンエッチング(RIE)が主流です。電場で加速されたイオンが特定方向に衝突することで、異方性の高い垂直エッチングを実現します。プラズマ密度や電子温度の制御が、加工速度・選択比・形状忠実度を決定づけます。
等方性・異方性エッチングの違いと制御
エッチングは反応の進行方向により、「等方性」と「異方性」に分類されます。どちらの特性を重視するかは、目的や構造によって異なります。
等方性エッチング
等方性エッチングは、縦横すべての方向に反応が進行します。ウェットエッチングが代表例で、一括処理や不要膜除去など形状精度が求められない工程で多用されます。
ただし、反応速度が高いと「アンダーカット」と呼ばれる現象が生じ、レジスト下の膜まで削れてしまうため、微細加工には不向きです。
異方性エッチング
ドライエッチングは異方性エッチングに分類されます。イオンの照射方向を垂直に制御し、側壁に堆積物を形成して横方向の反応を抑制します。これにより、コンタクトホールやビアホールなどの高アスペクト比構造を正確に形成できます。
プロセス設計で重視すべき選択比と保護膜制御
異方性エッチングを安定的に実現するには、材料間の選択比や側壁保護膜の形成が重要です。
たとえばシリコン酸化膜をエッチングする場合、炭素を含むガスを使うことでSi–O結合を切断し、同時に側壁へ保護膜を形成します。これが横方向の加工を抑制し、縦方向の精度を高める仕組みです。
ウェット処理でも反応速度や液性を調整すれば異方性加工は可能ですが、温度・濃度・流量などのパラメータ管理が難しく、装置コストも高くなります。そのため、量産プロセスではドライ方式が主流です。
エッチング装置の構造と放電方式
ドライエッチング装置は、プラズマ生成方式によって性能が大きく異なります。近年は高密度プラズマ化とダメージ低減を両立する装置開発が進んでいます。
容量結合型(CCP)と誘導結合型(ICP)
プラズマ放電の代表的な方式は2種類あります。
- CCP(Capacitively Coupled Plasma)方式:平行平板電極間に高周波電力を印加してプラズマを生成する。荷電粒子を効率的に加速できるが、ダメージがやや大きい。
- ICP(Inductively Coupled Plasma)方式:コイルに高周波電力を加え、誘導電界で高密度プラズマを生成する。電子密度が高く、低ダメージかつ高選択比の加工が可能。
先端半導体では、主にICP方式が採用されており、加工速度と形状制御を両立できる構造として普及しています。
生産性・選択性を高めるための装置開発
エッチング装置の改良は、生産効率と品質安定性の両立を目指して進化しています。近年では、AI制御やデータ解析を組み合わせたスマートプロセス化も加速しています。
生産性向上とコスト課題
先端ロジック・メモリでは、ダブルパターニングやマルチパターニングの採用により、エッチング工程数が増加しています。これが製造コスト上昇の一因となっており、装置の稼働率向上とプロセス短縮が大きなテーマです。
微細化に対応する高アスペクト比加工
チップの3次元化により、垂直方向への高精度な深堀エッチングが必須となっています。とくにコンタクトホールやビアホール形成では、高速で均一な加工と、側壁の形状安定が求められています。
主要エッチング装置メーカーの動向
ドライエッチング装置の分野では、日米の大手装置メーカーが競争を繰り広げています。米国のLam ResearchはICP方式を中心にシェアを拡大し、エッチングから周辺プロセス装置まで事業を拡張。Applied Materials(AMAT)は成膜装置のトップ企業でありながら、エッチング領域にも注力しています。
国内では東京エレクトロンと日立ハイテクが高精度装置で存在感を示し、グローバル市場で強い競争力を持っています。
まとめ
エッチング技術の進化は、半導体微細化の根幹を支える領域です。高密度・低ダメージのプラズマ生成、異方性制御、高アスペクト比対応など、多くの課題を同時に解決する必要があります。今後はAI解析や自動補正を活用した“プロセスインテリジェンス化”が進み、より高い生産性と品質安定性を実現する方向に進むでしょう。