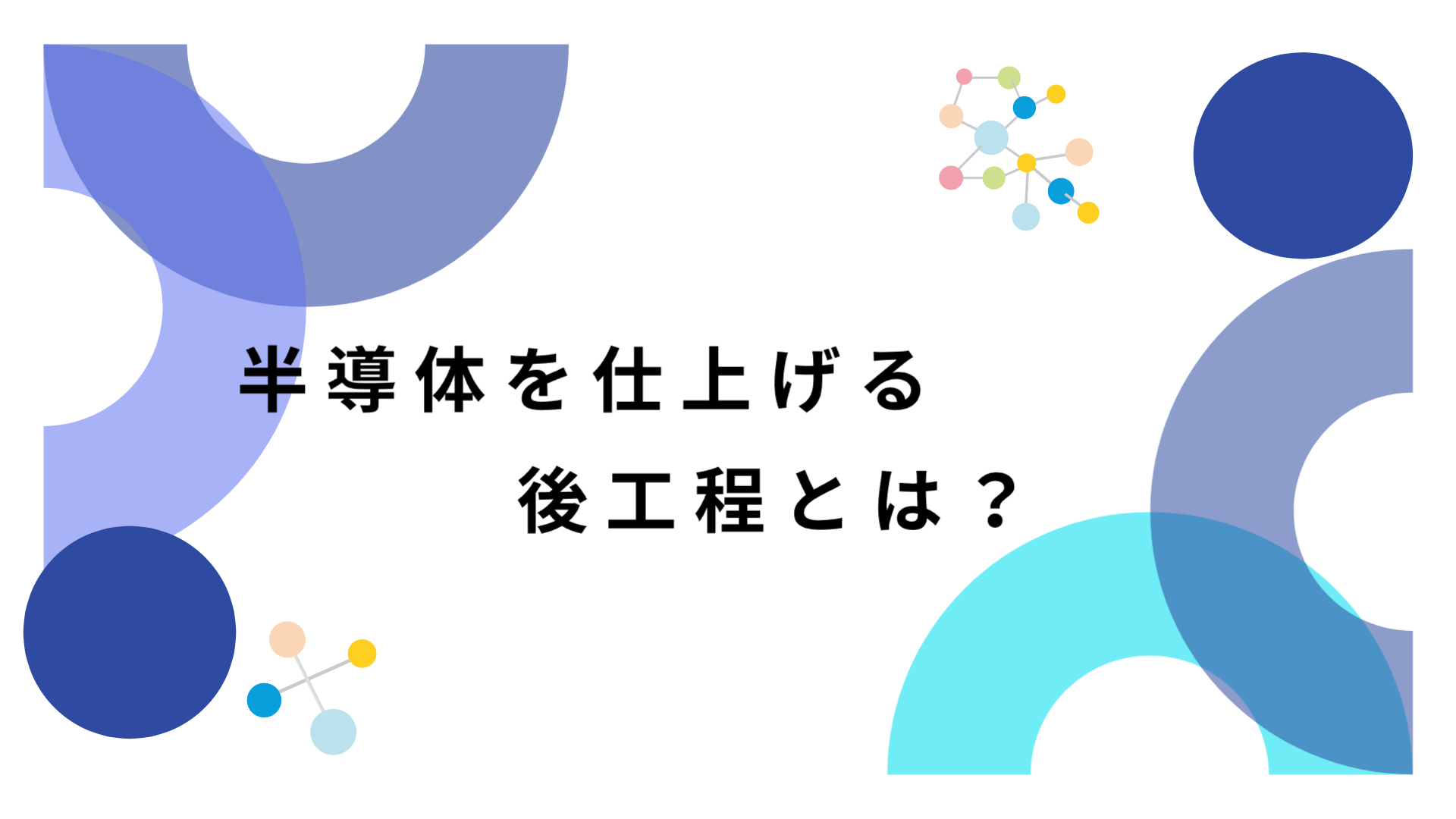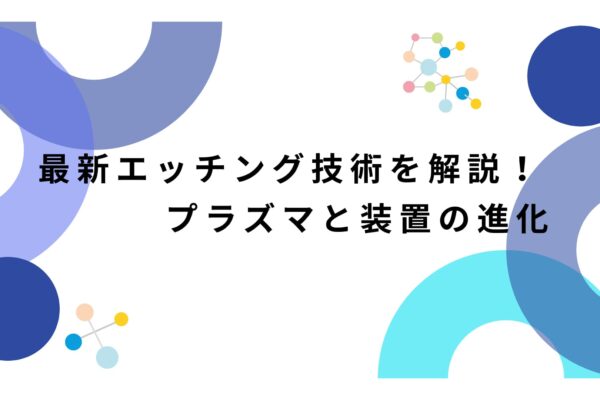半導体は、スマートフォンや自動車、医療機器など、あらゆる電子機器の中核を担う重要な部品です。その製造工程は、大きく前工程と後工程に分かれています。
前工程ではシリコンウエハー上に微細な回路を形成し、後工程ではそのウエハーからチップを切り出し、パッケージ化して最終製品として完成させます。特に近年、チップの小型化・高性能化が進むなかで、後工程の重要性は急速に高まり、市場規模も拡大しています。
本記事では、ダイシングやマウンティングといった後工程の具体的なプロセスから、品質検査、業界の最新動向までをわかりやすく解説します。工程の違いや意味を知りたい方の参考になれば幸いです。
半導体製造の工程とは?
半導体の製造工程は、大きく分けて回路部分を作る「前工程」と、回路を保護・接続する「後工程」の2段階に分かれています。それぞれの工程は専門的な装置と高い技術が要求され、製品の品質と歩留まりに直結する極めて重要なプロセスです。
まずは、それぞれの違いを簡単に解説しましょう。
前工程
前工程とは、半導体の回路部分を作成します。シリコンなどの原料から、ICチップのもととなる「シリコンウエハー」を作り出し、これにイオン注入や熱処理などの処理を施すことで回路を形成します。
これは半導体製品の心臓部を作る極めて重要なプロセスであり、微細化が進む現代では、極めて高度な装置・材料・プロセス制御が求められます。
この段階での精度や安定性が、最終製品の性能や信頼性に直結してしまいます。半導体の微細化が進むなかで、先端デバイス構造・装置技術の開発も急速に進んでおり、前工程は常に進化が求められる領域といえるでしょう。
後工程
半導体を最終製品として完成させる工程のことを、後工程といいます。ウエハーから個々のICチップを切り出し、基板に実装・配線し、最終的に外部と接続可能な形にパッケージングする一連の作業を指します。
前工程が「心臓部」なら、後工程は「完成された体」を作ります。高品質な半導体製品を社会に送り出すため、最終的な品質を保証する工程です。近年では、先端パッケージやファンアウト技術など新たなテクノロジーが登場しており、後工程の高度化と差別化が業界の競争力を左右する鍵となっています。
後工程が重要な理由は?
半導体は、精密機器の心臓部にあたるパーツです。わずかな誤差があるだけで、製品に重大な欠陥をおよぼす可能性があります。ここでは、後工程が重要な理由を詳しく解説しましょう。
製品の信頼性に直結するから
後工程では、外部からの衝撃や埃などから製品を守るために、封止作業を行います。この工程が不十分だと、湿気や汚れによって動作不良を起こしてしまいます。
特に車載用や産業用など、厳しい条件下で使用する製品にとっては、この工程が不十分だと製品の寿命が短くなる原因に。結果として、製品の信頼性の著しい低下を招いてしまうでしょう。
性能に関わるため
半導体は、高速で信号処理を実施しています。そのため、パッケージの放熱性や電気特性が性能に大きな影響を与えています。
特にスマートフォンでは、小型かつ高性能な半導体が必要不可欠です。後工程により、こうした性能が担保されなければ、動作不良を起こす原因になりかねません。
大量生産性とコストに直結するため
後工程では、たくさんのチップを効率的に処理しなければなりません。たとえば、数億単位の製造が必要なスマートフォンでは、後工程での自動化・省人化の効率化が、全体コストの大きな差につながります。
また、前工程で精密に作られたウェハーでも、後工程によって不良が出れば、製品価値はゼロになってしまいます。生産性・品質・効率のバランスを保つためには、
後工程のプロセスは?
後工程は、全工程で製造されたウエハーからICチップを切り出し、外部と接続できる形にパッケージ化、製品として出荷する為の工程です。ここでは、具体的なプロセスについて解説しましょう。
ダイシング
ダイシングは、ウエハー上に形成された複数のICチップを、1個ずつ切り離していく作業を指します。
半導体製造の後工程において、ダイシングは非常に重要な役割を担っています。この工程では、「ダイサー」と呼ばれる装置を用いて、シリコンウエハー上に形成された多数のICチップを精密に切断します。
切断面に欠けやクラックが生じると、その後の接合や封止工程に悪影響を及ぼすため、装置の刃の状態や切断速度、冷却液の制御など、細かな条件管理が求められます。特に近年ではウエハーの薄化が進んでおり、切断時に発生する振動や応力がチップを破損させないよう、低ダメージ加工やレーザーダイシングなどの技術が導入されています。
また、切り出されたチップの取り扱いにも細心の注意が必要であり、微小な破損や静電気による影響を防ぐため、専用のピックアップ装置やESD対策も徹底されています。ダイシングの精度は、後続工程や最終製品の品質を左右するため、半導体後工程の中でも特に繊細かつ高度な技術が要求されるプロセスです。
マウンティング
マウンティングは、ダイシングで切り出されたICチップをパッケージ基板やリードフレーム上に高精度で配置・固定する工程であり、後工程の中でも極めて重要です。近年の半導体実装では、フリップチップ技術やリフローマウンティング技術が主流です。
フリップチップ技術では、チップを裏返してバンプ(微小なはんだ球)を基板と直接接合するため、配線が短くなり、電気信号の伝送速度が向上し、パフォーマンスや熱特性にも優れます。
一方、リフローマウンティングは、チップを基板に配置後、加熱してハンダを再溶融させ接合する方式で、大量生産に適し、複数端子の一括接続と接合精度の高さが特長です。いずれの方法においても、チップと基板の間に生じるズレや接合不良は、動作不良や信頼性低下につながるため、ナノ単位での位置制御と導電性・耐久性の高い接合材料の選定が重要です。
マウンティング後には、光学検査・X線検査・電気的検査などで位置精度と接合状態を確認し、製品品質を保証するプロセスが欠かせません。
ワイヤーボンディング
ワイヤーボンディングは、半導体後工程において、ICチップ上の電極と、パッケージ基板やリードフレームとの間を微細な金属ワイヤーで電気的に接続する工程です。この接続により、チップ内部の信号を外部へ伝達可能にし、製品として機能させる役割を果たします。
使用されるワイヤーは、金・銅・アルミニウムなどで、いずれも高い導電性・接合性・信頼性があります。なかでも銅ワイヤーはコストと熱伝導性に優れ、量産向け製品で採用が進んでいます。
ボンディングには、ボールボンディングやウェッジボンディングの手法があり、材料やパッケージ形状によって使い分けられます。プロセス中では、接続点(ボンドパッド)の位置精度、ワイヤーの高さ・ループ制御、接合強度の最適化が重要となり、わずかなズレやたるみがチップの動作不良や断線につながるため、サブミクロンレベルの精密制御が要求されます。
また、接合は圧力・超音波振動・温度を組み合わせて行われるため、温度管理や圧力プロファイルの設計も歩留まりに影響します。工程後には、ワイヤーの接続状態や強度を確認するためのプルテスト、顕微鏡検査、X線検査などが実施され、最終製品の信頼性を確保する品質管理が徹底されます。
モールディング
モールディングは、ワイヤーボンディングを終えた半導体チップを樹脂で封止し、外部環境から保護する工程です。衝撃や湿気、温度変化、化学物質などからチップを守り、長期的な信頼性を確保するために必要不可欠です。
使用される樹脂には耐熱性・絶縁性・機械的強度が求められ、製品用途に応じた材料選定とプロセス管理が重要です。モールディング法は大きく気密封止と非気密封止に分類され、現在はコストと効率性に優れた非気密封止方式が主流です。
中でも金型モールド法が一般的で、溶融樹脂をチップに流し込んで硬化させるトランスファー方式や、樹脂にチップを浸すコンプレッション方式などがあります。これらの工程の違いは、下記の通りです。
| 方式 | 特徴 |
| トランスファー方式 | ・最も一般的で、量産品向けに採用されている ・チップへの圧力ストレスが高い ・生産効率が高い |
| コンプレッション方式 | ・チップや基盤を金型に設置し、樹脂を上から押し固めて成型する ・圧力が比較的低いため、均一に樹脂を広げられる ・サイクルタイムが長めで、大量生産には不向き ・トランスファー方式よりも導入コストがかかる |
樹脂の充填ムラや応力集中を避ける高精度な制御技術が求められ、封止不良は製品寿命や動作安定性に直結するため、モールディングは品質保証の観点からも極めて重要なプロセスです。
品質検査
後工程が完了すると、製品は出荷されます。できあがった製品がさまざまな環境下で耐えられるかどうか、さまざまなテストで品質を確認します。
たとえば、高温・低温・高湿度環境での動作確認をしたり、最大定格電圧を超える電気ストレス試験などを実施したりします。これらのストレステストは、潜在的な初期不良や信頼性の低い個体を検出するスクリーニングにも用いられ、品質の向上に寄与しているのが特徴です。
また、長期寿命試験(信頼性試験)では、実際の使用状況を想定して、加速条件下で数千時間にわたり通電・加熱を行い、時間経過による劣化や故障モードを解析します。さらに、温度サイクル・高温高湿ストレステスト、ESD耐性試験(静電気)なども実施され、各製品の用途に応じた信頼性要件(車載・通信・産業用途など)を満たしているかどうかを厳格に検査します。
これらの検査は、品質管理の最終段階であり、製品の長期安定供給と顧客信頼の確保に直結する重要なプロセスです。
半導体の後工程の市場動向は?
近年、半導体業界では後工程の市場が急速に拡大しています。これまでは微細加工技術が中心となる前工程が主流でしたが、チップの高性能化・高密度化が進む中で、パッケージングや実装といった後工程の技術にも高度な対応が求められるようになり、その重要性が増しています。こうした流れを受けて、日本企業も後工程分野での技術開発や生産体制の強化に力を入れており、国内外での市場拡大を目指す動きが加速しています。
2024年には、台湾の後工程大手・日月光投資控股(ASE)が北九州市での工場建設を検討しているという報道がありました。これは、熊本に進出しているTSMCとの連携を見据えた動きとされ、前後工程を国内で一貫して行う体制の構築につながるものとして関心を集めました。さらに、地政学リスクやサプライチェーンの多様化に対応するうえでも、後工程の国内回帰は大きな意味を持っています。
また、後工程の競争力を高めるうえで欠かせないのが、製造装置の性能と信頼性です。半導体産業は「装置産業」とも言われるほど、装置の精度が製品の品質や生産効率に直結します。高性能な装置を導入することで不良の抑制や生産の高速化が図れ、保守の効率化にもつながります。
今後の業界成長を支えるためにも、後工程では装置選定と技術革新がますます重要になっていくでしょう。
まとめ
後工程は、半導体を製品として機能させるための最終かつ重要な工程です。ダイシングや実装、接続、封止、検査といった各プロセスで高度な技術が求められ、品質・信頼性・性能のすべてを左右します。
近年では、後工程技術の進化がチップ性能の限界を押し広げる存在となっており、日本を含む世界各国で投資と開発が進められています。
また、製造装置の性能向上は生産効率や歩留まり改善にも大きく貢献しており、業界全体の競争力にも直結します。今後も後工程は、半導体産業の発展を支える要として、ますます注目されていくでしょう。